ともすれば儚げな印象を受けるその中で、瞳だけがきつく爛々と輝いている。
「・・・・今、何て言ったてめぇ」
射殺されそうな程の眼光にカルネは思わずたじろぐ。
大胆不敵な男が不覚にも、である。
「お前・・・何、ガキに凄まれてんだよ、情けねぇ」
思わず固まってしまったカルネを押しのけてパティが前に出る。
「驚かせて悪かったな。俺達は怪しいモンじゃねぇ。コックだ。
ここで働かせてもらえねぇもんかと思って来たんだが」
パティの言葉に子供の瞳から若干、険がとれる。
「コック? てめぇらが?」
値踏みでもするようにジロジロと二人を見た後、
「てめぇらみたいなボンクラには勤まらねぇぜ、きっと」
子供はニヤニヤしながら突き放すようにそう言った。
「何だと!!」
思わずいきり立ったカルネをパティは片手で制する。
「子供相手にムキになるんじゃねぇよ」
それから子供の方へ向き直り、重々しく口を開く。
「・・・・あんまり乱暴な口をきくもんじゃねぇぜ、女のコなんだから」
地雷をふんずけたのはパティだった。
目の前から子供の姿が消えた!!―と思った瞬間、厨房に大音響が響き渡る。
パティは股間にもの凄い衝撃を受け、後ろへとひっくり返った。
凄まじい早さで蹴り込まれたのである。
軽い体重を補って余りあるスピード。
急所にモロに受けたその衝撃は計り知れない。
その証拠に、パティは泡を吹いて後ろにひっくり返ったまま身動き一つしない。
反撃不能・戦闘不能だ。もしかしたら別な意味でも不能になってしまったかも知れない。
ふーふーと肩で息をしながら子供は次に絶句しているカルネを指差す。
「てめぇら、海の水で目ン玉洗ってから出なおして来いっ!!
俺は男だっ!!」
かくーん。
沈黙の中、カルネの顎が音をたてて落ちた。
かの有名な一流レストラン、バラティエの厨房には、現在何故か・・・・
目つきの悪い子供に、
泡を吹いて倒れている男と、
だらしなく大口を開けている男、
がいる。
このにっちもさっちもいかない状況を、扉の方より飛び込んできた一声が打破した。
「うるせぇぞっ、サンジっ!! てめぇの練習の為に厨房をあけてやってるんだぞ」
大きな影がゆっくりと厨房へ入ってくる。
堂々たる体躯。波瀾万丈なその半生を物語る深い皺と、威厳に満ちた顔。
悠然とした足取り。だが、その足音には交互に人工的な音が混ざっている。
かつて『赫足のゼフ』として名を馳せたその人だ。
その名を聞けばある者は恐れ、ある者は敬う。
そんな人物を前にしてもサンジは怯む様子を微塵も見せない。
「俺だって好きで騒いでるんじゃねぇや、クソジジイっ!!
大体、厨房が空なのはクソコック共が胸ヤケ起こしてぶっ倒れてるからじゃねぇか!!」
あろうことか、くってかかっている。
ますますあんぐりと口を開けたままカルネはその様子を見つめている。
ぎゃあぎゃあと喚くサンジの額に義足の底を押し当てると、ゼフはその足に軽く力を込める。
いとも容易く転がるサンジを見てゼフは僅かに微笑を浮かべたが、次の瞬間その顔を元の険しいそれへと変える。
それから見なれぬ男へ一瞥をくれる。
―何から話せばいいんだ―
心の準備ができないまま伝説的な勇名を持つ男の前に立たされ、カルネは酷く緊張していた。
なめられないようにと入れていた気勢はすっかり削がれてしまっている。
とりあえず世間話を、とカルネは舞い上がりながら口を開く。
「あ、あの・・・可愛らしいお孫さんですね」
それを聞いたゼフの眉がピクリと跳ね上がる。
一層険しくなったその顔を見て、カルネは自分が間違ったことを言ったのだと気づいた。
年の差から勝手に推測して孫だと思ってしまった、と。
あの子供はきっとゼフの孫ではないのだ。
伝説の男、ゼフならきっと今でも港、港に女がいるのだろう。この子もきっと・・・・・
「も、もしかして息子さんで?」
こうしてパティの後を追うように、カルネもまた地雷を踏んづけたのだった。
次の瞬間、自分の身に起こったことをカルネは理解できなかった。
理解できないまま吹っ飛ばされていた。
ゼフの義足は目にも止まらぬ速さでカルネの鳩尾を捕えていた。
泡を吹いて床に倒れる男二人。
息一つ乱すことなく、ゼフはその二人の顔を見比べてからサンジに問いただした。
「・・・・何だ、こいつらは?」
床の上で胡座をかいたまま、憮然とした表情でサンジは答える。
「知らねぇよ」
今でこそ、店の重鎮たる地位を築いているこの二人のバラティエ初入店はこのようにして幕を閉じたのである。
青い空の下でカルネはゆっくりと目を開ける。
船上は相変わらずの甘い香り。
初めてここに来た時もこんな風に目を覚ましたのだ。
意識が混濁する。どちらが夢だ?
サンジが行ってしまった方が夢なのか。
厨房からはいつものようにオーナーとやりあうサンジの怒鳴り声が聞こえてくるようなそんな気がしてならない。
カルネは寝そべったまま軽く頭を振った。
大きく息を吸って、半覚醒の脳に酸素を送り込む。
これが現実だ。
サンジのいない、これがバラティエの今なのだ。
少しばかり懐かしく、寂しい気持ちが蘇ったのは、この甘い香りの所為らしい。
明日に控えた品評会のことを考え、それからカルネは小さく笑った。
「何一人で笑ってんだ、気持ち悪ィ」
隣からはパティの声。
くっくっ、と笑いながらカルネは答える。
「いやぁよ、品評会の"裏の意味"に結局サンジの野郎は気づかなかったなぁ、と思ってよ」
のそりと身を起こしながら、パティも楽しげにその話に乗る。
「勝負ゴトには熱くなるからな、アイツ。毎年自分の作品のことだけで頭一杯だったろうよ」
カルネも半身を起こし、付け加える。
「それにアイツぁ、自分のことには鈍感なトコあるからなぁ」
そしてどちらからともなく。
「じゃあ、賭けるか? 次にヤツがこの店に来た時に"裏の意味"に気づいてるかどうか!!」
「よっしゃ! ノった!! 俺はなぁ・・・・・・・・・」
翌日。
春島に近づきつつあるゴーイングメリー号。
気候はすっかり安定し、適度な風が順調に船を先へと導いている。
それにしてもイイ陽気だ。
ポカポカである。
ゾロだけではなく、ルフィもウソップも果てはチョッパーまでもがのんびり昼寝を決め込んでも仕方ない。
そんなクルーの中、勤勉に働く男が一人。
「もうすぐ焼き上がりますからね、ナミさん」
調理場より振り返り、麗しの航海士嬢をその視界に映すと、サンジはウキウキとそう告げた。
甘い、何とも言えぬいい香りがナミの鼻腔を擽る。
お茶を片手にカリカリとペンを走らせていたその手が止まる。
「丁度一息入れたいトコだったから嬉しいわ」
「一息と言わず、二息でも三息でも入れましょう、一緒に」
"一緒に"のところを強調してからサンジは苦々しげな表情を浮かべる。
「にしても、レディにばっかり働かせやがってクソ野郎どもが」
「別にいいわよ、この陽気じゃあね。
それに、日誌書くのは私の趣味みたいなものだしね」
にっこりと笑うナミに思いきりつられるサンジ。
「そんな寛大なナミさんも素敵だv
・・・・・そんな優しいナミさんに、本日はスペシャルデザートを」
さくさくと切り分けた一片を皿に乗せてサンジはナミへと差し出す。
「これは俺の思い出のデザートなんですよ」
ナミの向かいに座るとサンジは頬杖をついて微笑んだ。
おいしい、おいしいと相好を崩すナミを幸せそうに見つめながらサンジは説明した。
バラティエには毎年この日に、常連だけを招いてのお菓子の品評会があったことを。
「・・・そこで俺が初めて1位を取ったのがコレなんですよ」
「ふーん、毎年かぁ。コックさんも大変ねぇ」
そう言ってナミはお茶へと手を伸ばしかけて、はたりと手を止める。
その手は日誌の日付の上にあった。
―3月2日―
―常連だけを集めて―
―品評会ですって!?―
「・・・・どうしました? ナミさん」
怪訝な顔をしているサンジ。
ナミはその顔をしげしげと見つめる。
―私のかんぐり過ぎかしら、いやでもきっと―
「ねぇ、サンジ君。その品評会って品評会だけなの?」
「いや、来るのは常連客だけなんで俺らも混ざってワイワイ騒ぐんですけどね。まぁ、ちょっとしたパーティーみたいなモンすかね」
それが何か?といった感じでサンジは答える。
ナミはサンジを見つめたまま、
―やっぱり、間違いないわ。でもってサンジ君は全然気づいてない?―
ナミはおもむろに日誌をサンジの目の前に広げる。
面食らった様子のサンジにナミは言う。
「サンジ君。よく見て!!」
「へっ? 日誌が何か???」
ナミはずずいと更に日誌を近づける。
「日付よ!!」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?」
「3月2日!!」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!?」
サンジは思わずナミの手から日誌を取り上げると、目の前で広げたまま硬直している。
そんなサンジにナミは決定的な事実を告げる。
「サンジ君の誕生日でしょ。
だから、きっとソレって品評会の名を借りたサンジ君の為のパーティーなんじゃないの?」
黙したままのサンジ。
爆弾を投げ込んだまま、ナミはそしらぬ顔デザートの残りに取り掛かり始めた。
そして、ナミがすっかり食べ終わった頃。
がばっ!!
日誌を傍らに置くとサンジはいきなりテーブルの上に突っ伏した。
そのまま身動き一つしない。
ナミは動じることなく、ゆっくりとお茶を飲み干した後のんびりとサンジに声をかける。
「ずーーーーーーーと気づかないでいたのね? サンジ君」
うー、という唸り声がテーブルを震わせている。
「・・・・耳、真っ赤よ。サンジ君」
笑いを噛み殺しながらナミがそう言うと、サンジはいきなり立ち上がりナミに背を向ける。
よっぽど顔を見られたくないらしい。
「ち、ちょっと、俺、風にあたってきますっ!!」
それだけを言うと、蟹のように横歩きしつつキッチンを後にする。
バタンと扉が閉まってからきっかり10秒後。
「うわーーーっ!!」
という叫び声と共にドカドカと階段を駆け上がる足音が聞こえてきた。
その途中で段を踏み外したような音を聞いてナミは今度は声をあげて笑った
海を渡る風は温かく、頬を冷やすのには全く役に立たなかった。
顔が熱い。
火でも吹きそうだ。
メラメラの実も吃驚だな、と下らないことを考えようとしてみたが、それは徒労に終わった。
キッチンの上、蜜柑畑の前に腰を下ろしたサンジの顔は果たして真っ赤であった。
顔を火照らせたままでサンジは、バラティエにいた頃の事を思い返してみる。
海上レストランができてから毎年開かれていた品評会。
ガキの頃は参加したくてしたくて毎年クソジジイに文句を言ってたっけ。
参加許可をもらってからはどうやって1位を取るかを。
1位を取ってからはどうやってそれを死守するかを。
そんなコトばかり考えていたのだ。
―トップを取れた時ぁ、嬉しかったなぁ―
とは言え、その時の自分の舞い上がりっぷりを考えると今となっては恥ずかしいだけだ。
ましてや、品評会にそんな意図が込められていた・・・かも知れないと考えれば尚更だ。
下にナミがいなければきっと叫んでいただろう。
「恥ずかしいコトすんじゃねぇーーーーーっ!! クソジジイーーーっ!!」と。
―ヤベエ、本当にかなり恥ずかしいぞ、こいつぁ―
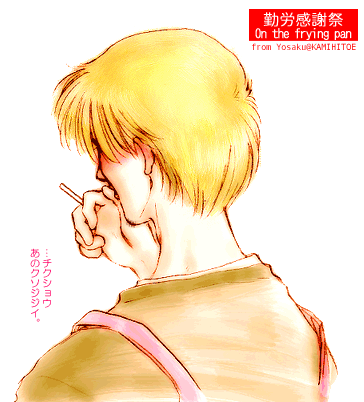
Special Thanx illust じょんじょんサマ
サンジの顔の赤みは全く引かない。
うるさい野郎共が眠っててよかったと思いつつ、ナミに先に知られてしまったことが何とも照れくさい。
―あぁ、畜生!!―
内心毒づくとサンジは気を静める為にポケットから煙草を取り出す。
軽く咥えて火をつけようとした瞬間、ふいに風向きが変わった。
キッチンから漏れる甘い香がふわりとサンジを包み込む。
サンジは煙草を咥えたまま、ライターをポケットに戻した。
―タマにはこんな気分も悪くねぇかな―
そう思ってしまった自分に思わず苦笑する。
遠い記憶。
騒がしく、心優しい連中。
遥かな故郷。
春風に乗る香りはどこまでも甘く、そして懐かしかった。